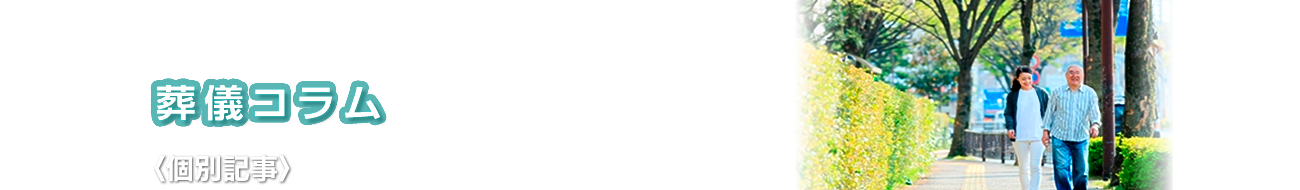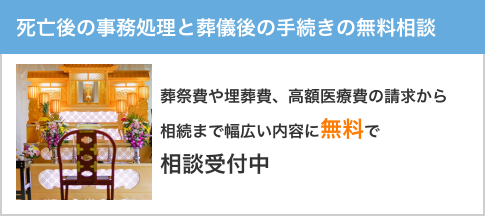2009(平成21)年から福岡県北九州市門司(もじ)区に拠点を移し、86歳の今でも精力的な活動を続ける画家でイラストレーターの黒田征太郎(せいたろう、1939〜)は、北九州の魅力について、こう語った。
「北九州って自然がとても目に入るところでしょ。だけど対極に工場群もあって、その対比が僕は面白いと言いたい。関門海峡一つにしたって、これだけ狭いのに太平洋と日本海を繋げてるわけでしょ。韓国の人が見たら『漢江より狭いじゃん』って言いますよ(笑)。最初に入ってきたやつ、怖かったと思うよ。それがずっと後に壇ノ浦の戦いがあったりしてね。すごいなぁ。そういうことを想像して、ずーっとおもしろいって思ってられるんですよ」(2025年3月31日)
黒田は「やっぱり、石炭や鉄で栄えてきたのに、時代が変わって切り捨てられてきたという歴史があって、それでもたくましく立ち直ってきた人たちがいて、昔ながらの情が残っている」と、単純に「面白い」、或いは「歴史ロマンの舞台」の側面だけではない「北九州」を見据えている。
このような黒田は、「福岡」或いは「北九州」出身、またはどこかから移り住んできたにしても、人生の大半を「北九州」で過ごしている、というわけではない。現在の大阪市中央区道頓堀に生まれ、すぐに兵庫県西宮市に移った。第二次世界大戦中の空襲で、現在の滋賀県東近江市に疎開した。その後、米軍軍用船乗組員になった。そこで「芸術」に目覚め、その才能が開花した。1992(平成4)年には、ニューヨークにアトリエを構えたりもした。このことから、「旅」「移動」、そしてそれらに伴う、「文化摩擦」「揺らぐアイデンティティ」「固定観念や価値観の変化」による「適応」「不適応」…など、昨今の「グローバル化社会」において顕在化している諸問題は、黒田の人生においては欠かせないものだったはずだ。また黒田は世界中の「面白い」ものを、いくらでも眺め、体験し、堪能してきたと推察されるのだが、いろいろな「ところ」がある「福岡」でも「北九州」を選び、そしてまた「北九州」でも「門司」を拠点として選び、「面白さ」を日々眺め、体験し、堪能している。そのような黒田が「北九州の面白さ」に関して、「これだけ狭い」関門海峡において戦われたあの、「壇ノ浦の戦い」を、取り上げたのは何故なのか。
ちなみに、平家一門が滅んだ「場所」である「壇ノ浦」は、黒田が住む今日の「福岡県」にはない。現在の山口県下関市、長門国赤間関(あかまがせき)に所在する。とはいえ関門(かんもん。馬関(ばかん。下関の別称)の「関」と門司の「門」を取った名称)海峡の下関と門司を結ぶ関門橋の、アルファベットの“A”を思わせる白い主塔と主塔の距離は、たった712mしかない。肉眼でも「下関」から「門司」、「門司」から「下関」を確認できるのだ。それゆえ、今日では連絡船のみならず、山陽新幹線、関門国道トンネルでも結ばれている「下関」と、「門司」を含む北九州市は、共に一体となって経済活動を続けている。その「近さ」ゆえに黒田は、川幅が1km以上に及ぶという韓国の漢江と比べ、「そのような(狭い)ところで起こった」壇ノ浦の戦いを取り上げたのだろう。
「祇園精舎の鐘のこゑ」
そして「壇ノ浦の戦い」といえば、小泉八雲(1850〜1904)の『怪談』(1904年)に収められた「耳無芳一(みみなしほういち)の話」と相まって、『平家物語』(13世紀頃の成立か。作者未詳)の冒頭の文章が、
「祇園精舎の鐘のこゑ、諸行無常のひびきあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわり
をあらはす。おごれる者もひさしからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もつひには
ほろびぬ、ひとへに風のまへのちりに同じ。」
全ての物事は常に存在・存続することはなく、古今東西、権勢を誇っていた人や国などは、いつか必ず衰微する。それはまさに春の夜の夢のように儚いものだ。勇猛な人物もいつかは、亡くなってしまう。それはまさに風に翻弄される小さな塵と同じようなものだ…と、栄耀栄華を極めた一族を描いた「物語」を超え、人間存在そのものの苛烈な現実を突きつける。
では、この文章で「要約」された平家一門の滅亡を決めた「壇ノ浦の戦い」とは、一体、どんな戦だったのか。
もともと、壇ノ浦を含む関門海峡一帯の海域は潮の流れが速い。このことを熟知していた平家方は、当初は有利に戦いを進めていた。しかし、それは「勝利」につながるものではなかった。源義経(1159〜1189)の猛攻、平家方の武将の裏切りに加え、偶然にも、潮流が西に変わったのだ。一気に平家方は悲劇の道へと突き進んでいく。
「私はどこに行くのか?」と尋ねる幼い安徳天皇(1178〜1185)に、その言葉が終わらぬうちに、祖母の二位尼(にいのあま、平時子(ときこ)、1126〜1185。平清盛(1118〜1181)の継室(けいしつ。後妻のこと))は「西方浄土へ」と答え、共に海の底に沈んだ。この二位尼の辞世の句が、
「今ぞ知る 身もすそ川の 御ながれ 波の下にもみやこありとは
(今こそわかるでしょう 伊勢神宮のそばを流れる五十鈴川(いずずがわ)のように、
伊勢(国を地盤とした)平氏の流れを汲むあなた様ですから、この荒波の下にも都が
あることを)」
だ。ここで言う「都」とは、我々が考える、政治・経済・文化の中心…で、それらに惹きつけられた人々が多く集まり、混雑を極めた「場所」、かつ海の底にあるという「竜宮城」ではない。恐らく、仏教における極楽浄土のことであろう。
また、安徳天皇と共にあった、三種の神器のひとつである宝剣もまた、同じ運命を辿った。
一説によると、源氏方3000艘に対し、1000余艘と伝わる平家方を率いた平知盛(とももり、清盛の四男。1152か?〜1185)、経盛(つねもり、清盛の異母弟。1124か?〜1185)、教盛(のりもり、清盛の異母弟。1128〜1185)、資盛(すけもり、清盛の嫡男・重盛(1138〜1179)の次男。1161〜1185)、有盛(ありもり、重盛の四男。1164〜1185)など、平家一門の精鋭たちも討ち死にしたり、自害したりするなど、皆、非業の死を遂げた。
清盛の三男・宗盛(むねもり。1147〜1185)と清宗(きよむね。1170〜1185)親子、時忠(ときただ、時子の弟。1130か?〜1189。)は源氏方に捕えられた。安徳天皇の母であり、高倉天皇(1161〜1181)の皇后である建礼門院徳子(とくこ。1155〜1214)も海に身を投げたものの、救い出された。生還したことは徳子にとって、果たして「幸せ」だったのだろうか…。
源氏の勝利に貢献し、鎌倉幕府の成立に尽力した三浦義澄
こうした「悲劇」にスポットが当てられているということはそもそも、『平家物語』冒頭の「祇園精舎の鐘のこゑ、諸行無常のひびきあり」(天竺に所在する祇園精舎の「無常堂」の鐘の音は、全ての物事が常住し得ないという、生滅の法を如実に物語る音色である)を導き出すことが前提であるのを、読者は忘れてはならない。確かに、平家一門を上記のように打ち滅ぼした「壇ノ浦の戦い」はもちろんのこと、200m以上の断崖絶壁から駆け降りるという奇襲・奇策をもって平家方を制した「一ノ谷の戦い」(1184年)の大将を務めた源義経(1159〜1189)は、実に生き生きと描かれている。しかしそれらの輝かしい猛攻ぶりは後の、実の兄・頼朝(1147〜1199)との対立を経て、落ちのびた奥州(現・岩手県西磐井郡)で自害することとなる「最期」によって、やはり義経は義経で、安徳天皇同様の「盛者必衰のことわり」(栄えている者は必ず衰えるという真理)を表していた。
この稿で、最終的には義経と「同じ」だったのかどうかを、考えてみたい人物がいる。その人物は1180(治承4)年、石橋山の戦い(相模国足柄下郡(あしがらしもぐん。現・神奈川県小田原市))で父・義明(よしあき。1092か1097か1102〜1180)に付き従って、平家方に敗れた頼朝を長らく助けた。その後、1192(建久3)年の鎌倉幕府樹立後の1209(承元3)年には、相模国の守護職に任じられるなど、重要な役割を果たした。相模国三浦郡矢部郷(現・横須賀市大矢部)を拠点とする武将・三浦義澄(よしずみ。1127〜1200)。平安時代中期(901〜1093)に遡るとされる土地の豪族・三浦氏の5代目当主だ。
三浦氏のルーツと本拠地
三浦氏のルーツと本拠地そもそも「三浦氏」は、初代・為通(ためみち。1010か?〜1083か?)が、陸奥国(現・岩手県北上川流域)の豪族・安倍(あべ)氏と陸奥国司との争いであった前九年の役(1050頃〜1062)で武功を挙げたことにより、戦いを率いた源頼義(よりよし。988〜1075)から、相模国三浦郡(現・横須賀市・逗子市・三浦市)を与えられた。そしてそこに衣笠城(現・横須賀市)を建て、居住したことに始まる。一族郎党は「三浦衆」「三浦輩」「三浦党」とも呼ばれた。
現在の一般的な「港湾」には、①おびただしい種類・数に及ぶ輸出入品の国内外へ/国内外からの輸送を支える物流システム②大小様々な工場での、ものの生産システム。それを支える、石油などの資源の輸入、完成品の国内外への積み出しシステム③先の2機能に関わる人々の活動、そして「外部」から、「夜景」「クルーズ」などの観光に訪れる人々をビジネスの対象とする、生活システムの3機能が備わっている。当時であっても、それらは大筋において変わらなかっただろう。そのような「場所」を押さえている豪族であるということは、三浦一族は時に「政治」すら動かしうる「力」を有していたとも言えよう。
時を経て、為道から数えて4代目・義明の長男で、義澄の兄でもある杉本太郎義宗(よしむね。1126〜1164)は、現在の三浦半島の東海岸を北上し、武蔵久良岐(くらき)郡(現・横浜市中区・西区・磯子区・金沢区・南区・港南区)の開発を手がけた。その中心地が後の武蔵六浦荘(むつらのしょう。現・横浜市金沢区)で、頼朝や後の執権・北条氏一門に、防衛的にも、そして今で言う「保養地」的な意味合いでも、重要視された「場所」のひとつだった。
三浦義澄が壇ノ浦の戦いに海軍力で功績を上げることができた経緯
こうした「土地柄」ゆえに、彼らは名だたる鎌倉武士たちの中でも、「海軍力」を誇る武士団だったと言われている。しかもその勢力は、「この辺り」だけではなかったようだ。全盛期の三浦一族は、北は陸奥国五戸(ごのへ。現・青森県三戸(さんのへ)郡)から、南は大隈(おおすみ)国(現・鹿児島県東部)に至る38ヵ国を支配下に置いていた。当時の日本は66ヵ国だったことから、半分以上の支配権を及ぼしていたことになる。何故そうなるのか。三浦氏に限らず、合戦時の敗者の所領は、勝者が大将から恩賞として賜る。その後、勝者は一族郎党をその所領に派遣し、支配を行うためだ。そのため、三浦氏が領した国々は内陸部だけではなかった。例えば、1186(文治2)年には、瀬戸内海の入り口で、太平洋にも通じた阿波国久千田(くちだ。現・徳島県阿波市)を領有していた。また、先に挙げた石橋山の戦いに敗れた頼朝が「安房(あわ)(現・千葉県南部)落ち」した際、道案内したのが今回取り上げる、義澄だった。「道案内」ができるということは、その土地に精通していなければ到底叶わない。それゆえ、日本中世史の研究家である鈴木かほる(1946〜)は、三浦一族が平安末期の時点で、安房国内も領有していたのではないか、と推察している。
かつて、大和(やまと。現・奈良県)や京(きょう。現・京都府)から東国方面に向かう際、東海道を進み、相模国(現・神奈川県)を横切って、御浦(みうら)郷(現・神奈川県三浦市)の走水(はしりみず。現・神奈川県横須賀市)の港から、海で総国(ふさのくに。現・千葉県)に至るのが「正しい道筋」だったという。それゆえ「この辺り」は、三浦氏が治めるようになる前からずっと、陸海の要衝の地だった。そうなると当然、後に「三浦水軍」と称された、三浦氏とその周囲の人々、或いは「水軍」をも含む「海賊衆」、すなわち三浦家支配以前から住んでいた土地の豪族・地侍・水主(すいしゅ。船頭以外の全ての船乗り)・漁師・海士(あま。海辺に住み、魚介類や海藻などを採集して暮らす人々)に、先祖代々継承されてきた航海術・漕船(そうせん)術に加え、国内各地の物資の流通や人々の交流、宋(960〜1279)との国際貿易を巧みに行う「折衝力」「交渉力」をも包括した、「海軍力」が培われていったのは、ごく自然な流れだったと言える。
元・三崎警察署長で郷土史家、そして地域をテーマにした童謡の作詞家でもある原博良(はらひろよし。1927〜)が「三浦水軍」の発祥として、三浦市三崎に鎮座する「海南(かいなん)神社」に祀られている藤原資盈(すけみつ。生年不詳〜866)を挙げている。海南神社の縁起によると、資盈は奈良時代(710〜794)の貴族で、740(天平12)年、当時の政治体制に憤り、大宰府(現・福岡県太宰府市)で挙兵し、死罪に処せられた藤原広嗣(ひろつぐ。714頃〜740)のひ孫だった。そのような「バックボーン」を有していたためだろうか。清和天皇(850〜881)の皇位継承時の争いで、その中心人物だった伴善男(とものよしお。811〜868)に賛同しなかったことから、讒言を受ける羽目になった。そこで当時、大宰府に在った資盈は御座船(ござぶね。高位の者が乗る豪華な船)で博多の港を出発した。そして864(貞観6)年11月に、現在の三浦市三崎に到着した。自分の「天運」に報いるためか、資盈は亡くなるまでの2年間で、三崎の海を荒らし回っていた房総の海賊を討ったり、里人たちにいろいろな学問や物事を教授したりしていたという。その死後、人々は資盈の海葬を行った後、花暮(はなくれ)岸壁に祠を建てた。それが982(天元5)年には、社殿が整えられた「海南(かいなん)神社」として三浦郡の総鎮守となったという。原が藤原資盈を「三浦水軍の発祥」と定義づけたのは、「三浦一族」とは直接の血縁関係はないものの、資盈が「この辺り」で行ったことそのもの、そしてそれが地域の人々に敬意をもって受け入れられ、死後はおろか、今日に至るまで大切に祀られていることによるものだろう。
壇ノ浦の戦いにおける三浦義澄の動き
話を「壇ノ浦の戦い」前後の三浦義澄に戻そう。当時「三浦党」を率い、1180(治承4)年に、当時平氏側についていた畠山重忠(はたけやましげただ、1164〜1205)によって、衣笠城合戦で討死する羽目になった父・義明から「三浦介(みうらのすけ)」という、国司(こくし。地方の国の行政・財政・司法・軍事を司った官吏)の次官を意味する称号を受け継いだ義澄は、頼朝より「相模国」を任されていた。
そんな中義澄は、1184(元暦元)年に源範頼(のりより。1150〜1193。頼朝の異母弟で、義経の異母兄)に従って、平氏追討に当たっていた。しかし、範頼が豊後(ぶんご)国(現・大分県)に向かうにあたり、義澄は瀬戸内海側の周防(すほう)国(現・山口県東南部)の警備を命じられる、それは「留め置かれた」格好だったため、内心、「いい気持ち」ではなかったはずだ。そんな折、現在の四国沿岸部を制圧していた源義経(1159〜1189)が、わずか数十艘だったものの、壇ノ浦を目指して周防まで進んでいた。大島津(おおしまのつ。現・山口県柳井市の柳井津)に義経軍が到着したことを知った義澄は、義経の元に駆けつけた。そこで義経に「自分を用いて欲しい!」と直訴したとする説もある。強い援軍を得たと感動したのだろう。義経は義澄に、「門司関(もじのせき。海関(かいかん、海の関所。当時は平家方の拠点だった)を見る者」として、自軍の先鋒役を命じたのだ。義澄はそれに喜んで応じ、すぐに壇ノ浦東方の沖津(おいつ。現・山口県下関市満珠島(まんじゅしま))に布陣を敷いた。それに応じ、500艘とも1000艘とも言われる平氏方も豊前国田浦(たのうら。現・福岡県北九州市田野浦)を背に、臨戦体制を整えた。実際に義澄がどのくらいの数の船を率いていたかは不明だが、少なくとも船数が多く、優勢と思しかった平氏側であっても「安心できない」状況だったと考えられる。
しかもこうした義経側の「動き」に追随する人々もいた。例えば1185(元暦2)年には周防国の舟船奉行を務めていた船所五郎正利(ふなどころごろうまさとし、生没年不詳)は、数十艘の船を提供した。それは摂津(現・大阪府北西部、兵庫県南東部)の渡辺(わたなべ。現・旧淀川(きゅうよどがわ)河口部)の武士団・渡辺党、熊野別当(熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の三山を統括する者)で、社僧でもあった湛増(たんぞう、1130〜1198)が率い、紀伊半島南東部の熊野灘・枯木(かれき)灘を根拠地とする熊野水軍や、伊予国を根拠地とする河野(こうの)水軍が味方についていたことが大きいだろう。更に、九州・四国を在地とする多くの武士たちまでもが、平氏方から源氏方に寝返ったとも伝えられている。
また、歴史学者の黒板勝美(くろいたかつみ、1874〜1946)などが指摘していた、当時の関門海峡の潮流が、東流から西流に変わること。または、合戦が繰り広げられた12時から16時頃には、潮流が静まっていたという説もある。
結果的に、人間がどうすることもできない「自然」さえもが源氏方を後押ししたということなのだろうか。それから先は、我々がよく知る、あの「悲劇」の結末を平家方が迎えたのである。
三浦義澄の優秀さを物語るエピソード
そうした意味で「キーマン」と言える義澄だが、壇ノ浦の戦いが始まる直前に、機転が利き、折衝力が巧みであることを物語るエピソードがある。『平家物語』巻11 「讒言(ざんげん)梶原」によると、名将・梶原景時(1140〜1200)が、「今日の先陣を切らせてください!」と申し出た。それに対し、義経が「自分がいなければ構わないが、自分がいるからだめだ」と拒絶した。すると景時が「それはよろしくない!あなたは大将軍じゃないか!」と反論する。義経は、「鎌倉殿(頼朝)が大将軍であって、自分はここで指揮を取ってはいるが、立場としてはお前たちと同じだ」と言う。それに景時は、「本来あなたは、侍の上に立てる人物ではない…」と吐き捨てた。義経はそれを聞き逃さず、「大体、お前は何という愚か者か!」と激昂した。それに対して景時は「何ということをおっしゃるのですか。私には鎌倉殿以外の主人はおりません」と言った。とうとう義経は、「憎たらしい男だ!」と、太刀に手をかけて立ち上がろうとする。景時も太刀に手をかけた。そこへ義澄はそばに使える土肥次郎実平(どいじろうさねひら、生年不詳〜1191か?)と共に2人の間に入り、義経に向かって「大事な戦いの前に、このような仲間割れをなさいますと、敵に力を与えるようなものです。そしてこのことが、鎌倉殿のお耳に入ると大変でございます」と進言した。すると義経は冷静になった。そうなると、景時も手が出せない。争いは鎮まり、2人はそれぞれ、自分の「持ち場」に身を落ち着かせた…
これらは単なる「小競り合い」「いくさの前の気持ちの昂り」で、「よくあること」だったのかもしれない。だが、「よくあること」ゆえに、もしもこの揉め事が義澄らによってうまく収められなかったとしたら。それどころか、火に油を注ぐ格好になってしまっていたとしたら、源氏・平氏の運命を決するあの合戦に、源氏方が大敗を喫してしまうどころか、「戦い」にもならない形で自滅していたかもしれないのだ。頼朝を長とする「鎌倉幕府」が成立できたかどうかも、怪しい雲行きになってしまう。そうなると冒頭の、「諸行無常」の響きに満ちた「祇園精舎の鐘の音」が、勝利を伝える歓喜の音色として描写されていたこととなり、我々がよく知る「滅びの美学」に満ちた『平家物語』ではない。勇猛果敢で、智謀知略に長けた英雄たちを挙げ、源氏方の「愚かさ」と対比させる形で、平家一門の人々を称賛する物語になっていたことであろう。
鎌倉幕府成立から亡くなる迄の三浦義澄
平氏や奥州藤原氏を滅ぼし、国内平定を果たした頼朝が京都に上がった1190(建久元)年、義澄は当時の礼装であった水干(すいかん)姿で、騎馬行列の先頭を行く頼朝のすぐ後ろに連なる10人の「重要人物」のひとりとして、付き従っていた。
そして征夷大将軍になった1192(建久3)年には、頼朝の使者として有力武将の比企能員(ひきよしかず、生年不詳〜1203)らを従えて、鶴岡八幡宮で除書(じょしょ。任命書のこと)を受け取る大役を担っていた。
更に1194(建久5)年には、義明慰霊のため、頼朝は三浦一族の本拠であった矢部郷(現・横須賀市大矢部)に、義明を開山とする臨済宗建長寺派の「義明山満昌寺(まんしょうじ)」を建立させた。本堂前の大木は、頼朝自らが植えたと伝わっている。
これらの事象から、壇ノ浦の戦い以前からの義澄と頼朝と深い関係が、壇ノ浦の戦いを経ても、継続していたことが読み取れる。
1199(建久10)年の頼朝の死後も義澄は、鎌倉幕府第2代鎌倉殿となった頼家(1182〜1204、在位1199〜1203)に仕えつつ、13人の有力武将からなる合議制裁判に参画したり、壇ノ浦の合戦直前に揉めた、あの、梶原景時を鎌倉から追放するための連判状に名を連ね、結果的に景時を失脚・自滅に導いたりするなど、鎌倉幕府を表からも裏からも支えていた。
そして「もうこれで自分の役目も終わった」ということか。梶原一門が滅亡した3日後の1200(正治2)年1月23日、義澄は亡くなった。
満昌寺にある三浦義澄の墓

義澄の墓とされるものは現在、満昌寺から京急線の京急久里浜(くりはま)駅方面に歩いて4分ほどの住宅地の奥にある、薬王寺旧跡(現・横須賀市大矢部)に所在する。鎌倉幕府成立以降、この地を義澄の兄である義宗の息子・和田義盛(1147〜1213)が治めていたことから、1212(建暦2)年、義宗や義澄の菩提を弔うために建てられたという。しかし、1876(明治9)年、1868(明治元)年の神仏分離令に始まる、廃仏毀釈の影響だろうか。薬王寺は廃寺となってしまった。しかし今日も、義澄の墓と伝えられる、凝灰岩でできた三重の大きな石塔は残っている。古い大きな石塔の両脇には、「平和」を取り戻した現代に整えられた真新しい石塔、そしてこれらを守るように取り囲む塀がある。そして塀の外側には、時代を感じさせる、苔むした小さな無数の石塔が残っている。先に登場した満昌寺によって、実に清潔に管理され、決して「放置」されているわけではない状況に、思わず安心させられる。
しかし例えば東京都三鷹市の玉川上水で心中した文豪・太宰治(1909〜1948)の遺体が発見された日であり、誕生日でもある6月19日に営まれる「桜桃(おうとう)忌」に、日本各地、老若男女を問わない多くの太宰ファンたちが墓所・禅林寺(ぜんりんじ)に出向き、お墓に、生前の彼が好んだたばこやお酒を供え、香華を手向ける様子が「三鷹の風物詩」になっている状況を思うと、義澄の墓所の「静か」「寂しそう」な雰囲気は否めない。もちろんそれらの雰囲気は、かつて多くの人々で賑わっていた地方都市の商店街が、近在の大規模工場などの閉鎖・撤退、またはアジア圏への移転。或いは東京や大阪などの「都会」に出て行ってしまったことによる人口減や、住民の少子高齢化などの影響でほとんど閉店してしまい、人通りも無くなってしまった「シャッター商店街」に漂う「静か」「寂しそう」とは、必ずしも同じものではないが、「忘れられている」という点では、もしかしたら重なる部分があるのかもしれない。
三浦義澄もまた盛者必衰の道を辿ったと言えるか
冒頭で義澄のことを「最終的には義経と『同じ』だったのかどうかを考えてみたい」と問題提起した。墓所の「静か」で「寂しそう」な現在の雰囲気もまた、三浦の港や水軍を率い、鎌倉幕府初代将軍の頼朝を支えた義澄であっても、生きとし生けるものが等しく背負った「死なねばならない」宿命ゆえに、やはり「盛者必衰のことわり」が当てはまってしまう。
もちろん、国民的ヒーローとして、例えば織田信長(1534〜1582)、豊臣秀吉(1537〜1598)、徳川家康(1543〜1616)がいる。彼らを主人公とした小説を読んだり、ドラマや映画を観たりしている熱狂的な歴史ファンは多いだろうが、果たして彼らの命日にお墓参りをしたり、そこで営まれる法要に参加したりするほどの「ファン」は、太宰ほどいないだろう。
また、薬師寺そのものが廃寺になってしまったので仕方がないとはいえ、例えば2023(令和5)年には、浅草の浅草寺やアメ横、上野動物園や東京国立博物館などで知られる、東京都台東区を訪れた観光客は3862万人。そのうちの外国人観光客は442万人。その年の外国人観光客数は3687万人だった。国内外の観光客が何かのきっかけで義澄のものとされる墓所に大量に押しかけても、それはそれで「問題」だ。例えば今年の8月4日には、ひとりのオーストラリア人男性が、何の縁もゆかりもない山梨県富士吉田市内の霊園で、お供え物の缶酎ハイを一気飲みする様子を収めた動画をSNS上に投稿したことが大騒ぎになってしまった。しかもこの男性は、別の日に卒塔婆を引き抜いて振り回したり、モデルガンでふざけたり、お供え物のウサギの置物に触ったりしていた動画もアップロードしていたという。
この男性の行為は決して許されるものではないが、「異国への旅」に多くの人々が押しかけ、時に「狼藉」を行うようになったのは、今に始まった事ではない。ドイツ文化論やヨーロッパ紀行文学を専門とする森貴史(1970〜)によると、11世紀末〜13世紀のヨーロッパでは「巡礼」という宗教的儀式がさかんで、多くの人々がキリスト教の聖地・イスラエルのエルサレムや殉教者の墓を訪れていた。その際、イエス・キリストが磔にされたゴルゴダの丘の土や石、そこから足を伸ばし、同国北部の、イエスが幼い頃から宣教生活に入るまでを過ごしたナザレで、聖母マリアが汲んだという伝説がある泉の水などを、「聖地を訪れた証」として持ち帰っていた。それらの行為は地元住民からすると、迷惑と捉えられていたという。
それゆえ国内外の多くの旅行者の「関心」が何かのきっかけで急に高まり、薬師寺旧跡周辺で、京都や富士山などで顕在化している「オーバーツーリズム」問題が引き起こされても大問題だ。周辺の道路や墓所が観光客の残したゴミだらけになってしまったり、義澄の墓とされる三重塔を「御利益がある」などと削り取られたり、お供え物を勝手に飲み食いされたりすることを思うと、今のように「静か」「寂しい」墓所だったほうが、地下で眠る義澄のためになることは言うまでもない。鎌倉幕府そのものはとっくの昔に滅んでしまったが、義澄の魂は、かつて一族が領していた相模國三浦郡の安寧を見守ってくれているはずだ。とはいえ、「おごれる者もひさしからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もつひにはほろびぬ、ひとへに風のまへのちりに同じ」と記された未来が、薬王寺旧跡を含む横須賀市・逗子市・三浦市を訪れなければいいのだが…
参考文献
■菊池武「海のもののふ、三浦水軍 <三浦>」権守桂城(編)『かながわ史話:歴史の点描・民間伝承』1981年(36-38頁)昭和書院
■原博良『栄光の三浦水軍』1982年 三浦商工会議所
■田辺久子「三浦家」株式会社オメガ社(編)『地方別日本の名族 4 千葉県 埼玉県 神奈川県』1989年(165-198頁)新人物往来社
■松岡久人「海賊衆」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典』第3巻 1983年(70-71頁)吉川弘文館
■奥富敬之『相模三浦一族』1993年 新人物往来社
■原博良「特別公演『橘の国』」鶴見歴史の会(編)『郷土つるみ』第38号 1994年(2-10頁)鶴見歴史の会
■安田元久「壇ノ浦の戦」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典』第9巻 1989/2003年(353頁)吉川弘文館
■三浦勝男「三浦氏」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典』第13巻 1992/2004年(260頁)吉川弘文館
■三浦勝男「三浦義澄」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典』第13巻 1992/2004年(265-266頁)吉川弘文館
■「薬王寺旧跡(やくおうじきゅうせき)」『横須賀市』2010年11月1日
■下田奈津美「熊野別当と熊野水軍 −湛増期における熊野水軍の動向」京都学園大学人間文化学会学生論文編集委員会(編)『人間文化学部学生論文集』第11号 2013年(228-240頁)京都学園大学人間文化学部
■「薬王寺跡」『鎌倉遺構探索』2015年7月9日
■古川日出男(訳)『池澤夏樹個人編集 日本文学全集 9 平家物語』2016年 河出書房新社
■水原一(校注)『新潮日本古典集成 <新装版> 平家物語 下』2016年 新潮社
■水原一(校注)『新潮日本古典集成 <新装版> 平家物語 下』2016年 新潮社
■「ヨコスカDiscovery 第23回 大矢部に三浦一族の史蹟を訪ねる」『まなびかんニュース』2016年1月号(6頁)横須賀市生涯学習センター まなびかん
■「三浦一族歴史めぐり 20 海南神社」『Monumento』2016年2月23日
■山田順子『海賊がつくった日本史』2017年 実業之日本社
■川井康『日本中世の歴史 3 源平の内乱と公武政権』2009/2021年 吉川弘文館
■高橋秀樹『対決の東国史 2 北条氏と三浦氏』2021年 吉川弘文館
■鈴木かほる『幻の鎌倉執権三浦氏 関白九条道家凋落の裏側』2022年 清文堂
■「薬王寺旧跡・三浦義澄の墓|鎌倉幕府創設に貢献した十三人の合議制の一人の墓所」『三浦半島日和』2022年1月13日
■谷合伸介「Café des 三浦一族 第3回 三浦一族ゆかりの地 大矢部」幻の寺院跡、大谷部」『まなびかんニュース』2022年7月号(12頁)横須賀市生涯学習センター まなびかん
■中三川昇「Café des 三浦一族 第10回 幻の寺院跡、大谷部 『薬王寺遺跡』」『まなびかんニュース』2023年3月号(12頁)横須賀市生涯学習センター まなびかん
■台東区文化産業観光部観光課(編)『令和5年 台東区観光統計・マーケティング調査 報告書』2024年 台東区文化産業観光部観光課
■「『六浦藩』の歴史 神奈川県横浜市に唯一存在した藩」『戦国ヒストリー』2024年8月22日
■「国家は『旅』をどう利用してきたのか 歴史たどると迷惑行為も昔から」『朝日新聞』2024年11月14日
■中丸満「鎌倉幕府を支えた“三浦一族とゆかりの地・横須賀”」『WEB歴史街道』2022年8月5日/2024年12月16日